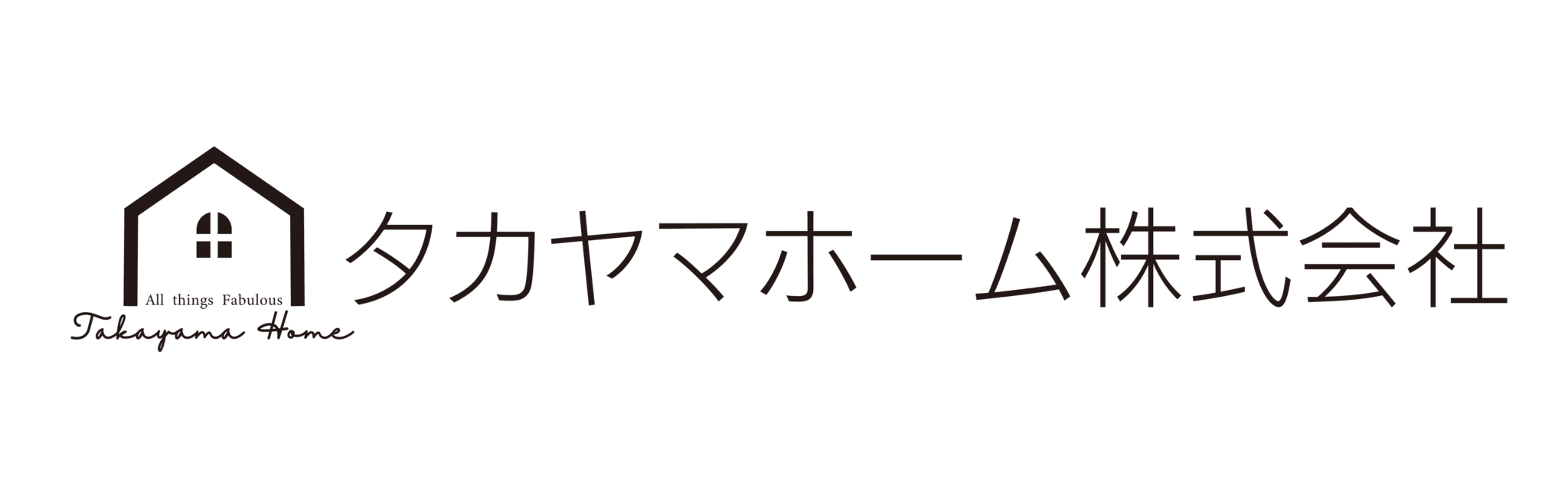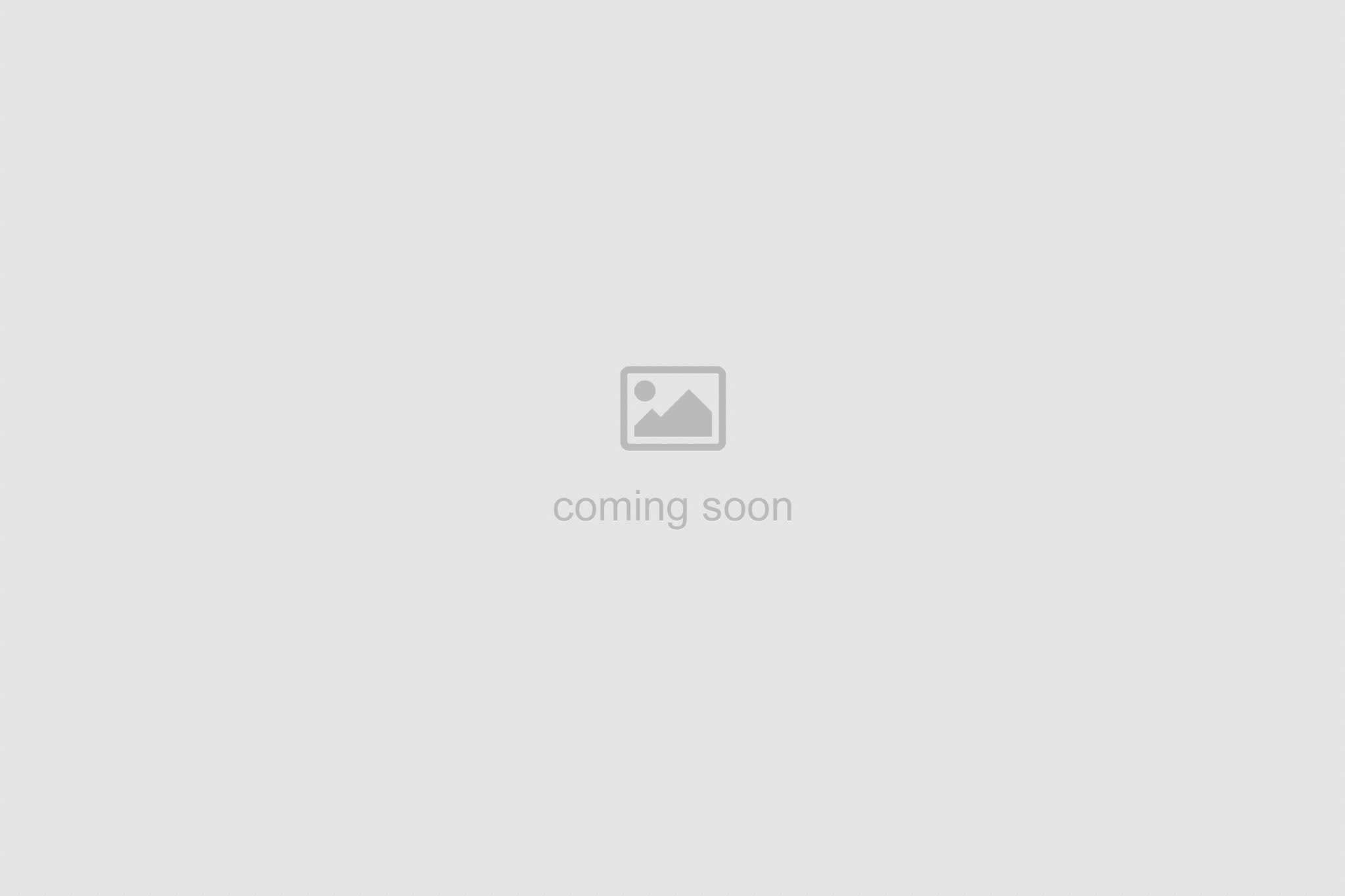100年住宅Q&A
弊社に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。
Q&A(お客様からのよくあるご質問と回答)
A:お答します
まず、家の構造木材を腐らせないことが大原則となります。そして、木材の天敵といえば、きのこの仲間である木材腐朽菌です。木材腐朽菌は、温度と湿度の条件がそろうと繁殖します。では木材腐朽菌の活動を抑えるには、どうすればよいのでしょうか。その方法と解決策として、おおまかに次の3つがあります。
?空気を遮断する。⇒(水中に浸す)
?水分を抑える。⇒(乾燥させる)
?温度を一定にしない。⇒(自然環境に近づける)
この3つの条件のうち一つでもクリアしていると、木が腐ることはありません。 (1)の水中に浸す方法というのは、ちょっと驚かれるかも知れませんが、一例をあげますと、約400年前に築城された江戸城の石垣を支えているには、お堀の水の下に組まれた丸太です。これは、昔の職人さんたちが水の中は空気に触れないことで木の中の腐朽菌が繁殖しないことを知っていたからです。それにしても、400年以上も前からこうした高度な技術知識を持っていたのには驚きです。 しかし、ただ腐らないからといって、水中に家を建てることはできません。地上の家において木を腐らせないただ1つの方法は、均一に人工乾燥させた木材を用い、長もちさせる方法を備えた工法で家を建てることです。
まず、家の構造木材を腐らせないことが大原則となります。そして、木材の天敵といえば、きのこの仲間である木材腐朽菌です。木材腐朽菌は、温度と湿度の条件がそろうと繁殖します。では木材腐朽菌の活動を抑えるには、どうすればよいのでしょうか。その方法と解決策として、おおまかに次の3つがあります。
?空気を遮断する。⇒(水中に浸す)
?水分を抑える。⇒(乾燥させる)
?温度を一定にしない。⇒(自然環境に近づける)
この3つの条件のうち一つでもクリアしていると、木が腐ることはありません。 (1)の水中に浸す方法というのは、ちょっと驚かれるかも知れませんが、一例をあげますと、約400年前に築城された江戸城の石垣を支えているには、お堀の水の下に組まれた丸太です。これは、昔の職人さんたちが水の中は空気に触れないことで木の中の腐朽菌が繁殖しないことを知っていたからです。それにしても、400年以上も前からこうした高度な技術知識を持っていたのには驚きです。 しかし、ただ腐らないからといって、水中に家を建てることはできません。地上の家において木を腐らせないただ1つの方法は、均一に人工乾燥させた木材を用い、長もちさせる方法を備えた工法で家を建てることです。
A:お答えします
鉄骨やコンクリ−トは見た目丈夫そうに見えますが、単なる風説です。木は、耐久性・強度などト−タルわたって最良の建材です。まず木の性質をよく知っていただくことから、木の寿命の誤解を解いていただくことが大切です。
木は驚くべき生命力があります。木は伐採されてから100年間成長しつづけます。そして100年をピ−クとして強度や剛性が緩やかに下降します。つまり、はじめから100年は保証されているのです。木は、乾燥状態をよくしておくと何百年でももちます。
フィンランドに行くとログハウスがたくさん建っていますが、みんな300年の耐久性があるそうです。その理由はとても簡単で、乾燥して化石状態になっている立ち枯れ材(シルバ−パイン材)を使用しているからです。乾燥させることがいかに重要であるか、おわかりになると思います。
カナダ・バンク−バ−の日本領事館のある団地では、100〜150年以上の住宅(木造ツーバイフォー)が多く現存しています。北米やカナダでは30年までは新築、50年たったら中古といわれています。それだけ木造住宅における耐久価値が違うのです。木造住宅の寿命をあれこれいうのは日本人だけです。
また、何百年の寿命を誇り、社会的ストックされているフランスの石造りの家。実は中身が全て木造で骨組みされていて、外壁だけが石造りであることをご存じでしたか?
それだけ木は堅牢かつ耐久性があると認識されているのです。
鉄骨やコンクリ−トは見た目丈夫そうに見えますが、単なる風説です。木は、耐久性・強度などト−タルわたって最良の建材です。まず木の性質をよく知っていただくことから、木の寿命の誤解を解いていただくことが大切です。
木は驚くべき生命力があります。木は伐採されてから100年間成長しつづけます。そして100年をピ−クとして強度や剛性が緩やかに下降します。つまり、はじめから100年は保証されているのです。木は、乾燥状態をよくしておくと何百年でももちます。
フィンランドに行くとログハウスがたくさん建っていますが、みんな300年の耐久性があるそうです。その理由はとても簡単で、乾燥して化石状態になっている立ち枯れ材(シルバ−パイン材)を使用しているからです。乾燥させることがいかに重要であるか、おわかりになると思います。
カナダ・バンク−バ−の日本領事館のある団地では、100〜150年以上の住宅(木造ツーバイフォー)が多く現存しています。北米やカナダでは30年までは新築、50年たったら中古といわれています。それだけ木造住宅における耐久価値が違うのです。木造住宅の寿命をあれこれいうのは日本人だけです。
また、何百年の寿命を誇り、社会的ストックされているフランスの石造りの家。実は中身が全て木造で骨組みされていて、外壁だけが石造りであることをご存じでしたか?
それだけ木は堅牢かつ耐久性があると認識されているのです。
A:お答します
最近、中断熱・中気密住宅という言葉を、特に南の地域でよく耳にしますが、これは大変見当はずれのことです。それでは北の冷蔵庫と南の冷蔵庫は、断熱・気密性能が違っていいんですか?というのと同じことなんです。
断熱・気密性能はエネルギ−の熱損失係数(Q値)で決められています。この数値の小さいほど熱が逃げにくいことが、省エネルギー性能の証明になります。北国では冬の暖房がかせないように、南国で夏の冷房はかかせません。「南の地域だから熱損失係数(Q値)を無視しても構わない」ということにはならないのです。
右下の図表をご覧下さい。これは、世界各国及び日本の各地域のQ値を比較したものですが、残念ながら暖房としての省エネルギー基準でしかありません。省エネルギーの視点から考えると、冷房の基準もあってしかるべきです。また、?地域、?地域も?地域と同じQ値になるべきで、南北に格差があってはならないはずです。こうした現状によって中断熱・中気密住宅という家がはびこってくるわけです。
それに、中断熱・中気密構造にすると、空気のイタズラ現象が生じます。それはどういうことかというと、断熱材を壁にびっしり入れないと空気が滞留することになります。そして内・外気の温度が急激に変化すると、その温度差により壁の中の空気が冷やされて、壁体内結露を起こしてしまいます。ですから空気のイタズラを防止するには、高断熱・高気密がセットでなければ絶対ダメです。
先頃、国が次世代省エネルギー基準を発表しましたが、これは地球温暖化防止のための京都会議で日本が公約した[1990年の実績よりも6%のCO2の削減]を2010年までにどうしても実行しなければならないという事情がその背景にあります。住宅の性能を高めることが、省エネルギーすなわちCO2の削減に貢献するという当たり前のことが、やっと時代の趨勢になったわけです。
● CO2を大幅に削減した省エネルギー住宅をつくり、地球温暖化の防止に努める。
● 家の解体が大型ゴミ(産業廃棄物)としてダイオキシンの発生など社会問題にもなっている現状をしっかり認識し、すぐ建て替えなければならないような家をつくらず、100年もつような耐久性のある家をつくる。
● 建て替えの際、ウレタンパネル等をもう一度再生させて家づくりを行う。リサイクル対応の工業化住宅として、省資源・リサイクル社会に貢献する。
以上の3点がホンモノの高性能住宅の技術面における重要なポイントとなりますが、プラスして今後は、お客様保護に立った性能保証がますます大切になってきます。つまりは、構造安全性、省エネルギ−性、耐久性、遮音性、防耐火性等の性能表示が項目ごとにはっきり明記した性能保証をすることが義務づけられ、もし家自体に瑕疵(かし)がある場合は、きちんとした保証をしなければならない時代になってきました。
これは、品質等に自信のない住宅メーカーにとっては困ったことになったわけです。つまりは、性能保証=瑕疵保証が確立している住宅メーカーだけが生き残れるわけです。
最近、中断熱・中気密住宅という言葉を、特に南の地域でよく耳にしますが、これは大変見当はずれのことです。それでは北の冷蔵庫と南の冷蔵庫は、断熱・気密性能が違っていいんですか?というのと同じことなんです。
断熱・気密性能はエネルギ−の熱損失係数(Q値)で決められています。この数値の小さいほど熱が逃げにくいことが、省エネルギー性能の証明になります。北国では冬の暖房がかせないように、南国で夏の冷房はかかせません。「南の地域だから熱損失係数(Q値)を無視しても構わない」ということにはならないのです。
右下の図表をご覧下さい。これは、世界各国及び日本の各地域のQ値を比較したものですが、残念ながら暖房としての省エネルギー基準でしかありません。省エネルギーの視点から考えると、冷房の基準もあってしかるべきです。また、?地域、?地域も?地域と同じQ値になるべきで、南北に格差があってはならないはずです。こうした現状によって中断熱・中気密住宅という家がはびこってくるわけです。
それに、中断熱・中気密構造にすると、空気のイタズラ現象が生じます。それはどういうことかというと、断熱材を壁にびっしり入れないと空気が滞留することになります。そして内・外気の温度が急激に変化すると、その温度差により壁の中の空気が冷やされて、壁体内結露を起こしてしまいます。ですから空気のイタズラを防止するには、高断熱・高気密がセットでなければ絶対ダメです。
先頃、国が次世代省エネルギー基準を発表しましたが、これは地球温暖化防止のための京都会議で日本が公約した[1990年の実績よりも6%のCO2の削減]を2010年までにどうしても実行しなければならないという事情がその背景にあります。住宅の性能を高めることが、省エネルギーすなわちCO2の削減に貢献するという当たり前のことが、やっと時代の趨勢になったわけです。
● CO2を大幅に削減した省エネルギー住宅をつくり、地球温暖化の防止に努める。
● 家の解体が大型ゴミ(産業廃棄物)としてダイオキシンの発生など社会問題にもなっている現状をしっかり認識し、すぐ建て替えなければならないような家をつくらず、100年もつような耐久性のある家をつくる。
● 建て替えの際、ウレタンパネル等をもう一度再生させて家づくりを行う。リサイクル対応の工業化住宅として、省資源・リサイクル社会に貢献する。
以上の3点がホンモノの高性能住宅の技術面における重要なポイントとなりますが、プラスして今後は、お客様保護に立った性能保証がますます大切になってきます。つまりは、構造安全性、省エネルギ−性、耐久性、遮音性、防耐火性等の性能表示が項目ごとにはっきり明記した性能保証をすることが義務づけられ、もし家自体に瑕疵(かし)がある場合は、きちんとした保証をしなければならない時代になってきました。
これは、品質等に自信のない住宅メーカーにとっては困ったことになったわけです。つまりは、性能保証=瑕疵保証が確立している住宅メーカーだけが生き残れるわけです。
A:お答します
ウレタンは軟弱な地盤の補強剤として使われるほど、圧縮強度が強い素材です。FPの家のウレタン断熱パネルは、こうしたウレタンの特質を最大限にいかし、100年住宅にふさわしい剛性と堅牢さを備えています。しかし、最近類似した住宅がいろいろ出回っています。お客様によってはウレタンを使っているから、みんな同じと思っている方が結構多いのではないでしょうか。「FPの家」の圧縮強度は他のウレタン(特に現場発泡方式)とは比べものになりません。圧縮強度が100年住宅においていかに欠かせないものであるかということを、もう一度復習してみましょう。
(1)まず、硬質ウレタンを木枠パネルに注入しながら約20〜30分程プレス機で荷重をかけて化学反応させ、自由発砲を抑えて、より高密度なウレタン断熱パネルを完成させます。
(2)つまり、圧力をかけるため密度が他のウレタン断熱メーカーよりはるかに高いのです。実際にウレタンの断面をみると、目が細かくなっているのが一目瞭然でわかります。
(3)そして、なぜ「FPの家」はウレタンを木枠に接着する方法をとっているのか?接着することで木とウレタンのそれぞれの剛性と強度が相乗効果をもたらし、圧縮強度がグーンとパワーアップするからです。地震のときは左右に揺れますが、こうした揺れにウレタン断熱パネルの圧縮強度が抜群の効果を発揮するのです。
(4)ウレタン断熱パネルを面構造にし、さらに剛性と堅牢さを維持させます。
ウレタンでもこんなに違う![工場生産型と現場生産型] ウレタン発砲は大変デリケートな素材なため、温度や湿度によって品質の出来不出来が左右され、その品質管理は非常に難しいのが特徴といえましょう。ウレタンは大別すると工場生産型と現場生産型があります。では、品質において工場生産型と現場生産型ではどのように違うのか、比較してみましょう。
<工場生産型>FP断熱パネル
●FP断熱パネルは、前者の工場生産型で、温度・湿度管理がしっかり行き届いており、四季の気候変化に合わせた原材料ブレンドをしています。また、朝・昼・夜毎に厳しく製品チェックをし、ムラのない一定な品質管理がなされています。工場で生産される注入式ウレタンパネルは、決められた体積に対する原材料をコンピュータで計算し、注入・圧力プレスして一定の大きさに成形します。したがって高密度なウレタンパネルが出来上がり、ウレタンのもっている性能が十分に発揮されます。
●また、FP断熱パネルは性能劣化がないため、何度でもリサイクルが可能です。
<現場生産型>現場発泡ウレタン
●現場発泡ウレタン(フリー発砲)は、後者の現場生産型で、ウレタン発砲の重要なポイントとなる温度・湿度管理に対応できません。また、原材料ブレンドの適切なコントロールができません。発砲量や厚さも一定ではなく、表面が凸凹しています。このようなムラの多い状態では測定もできませんし、性能・品質が曖昧となっています。
●さらに、現場発泡ウレタンは、工場生産の注入パネル1?当たり3分の2の量しか原材料を使用していませんので、ウレタンの性能が充分に発揮されません。
●また、将来、建物を解体する時、化学製品の分別回収になるため、相当なコストがかかることが予想されます。
ウレタンは軟弱な地盤の補強剤として使われるほど、圧縮強度が強い素材です。FPの家のウレタン断熱パネルは、こうしたウレタンの特質を最大限にいかし、100年住宅にふさわしい剛性と堅牢さを備えています。しかし、最近類似した住宅がいろいろ出回っています。お客様によってはウレタンを使っているから、みんな同じと思っている方が結構多いのではないでしょうか。「FPの家」の圧縮強度は他のウレタン(特に現場発泡方式)とは比べものになりません。圧縮強度が100年住宅においていかに欠かせないものであるかということを、もう一度復習してみましょう。
(1)まず、硬質ウレタンを木枠パネルに注入しながら約20〜30分程プレス機で荷重をかけて化学反応させ、自由発砲を抑えて、より高密度なウレタン断熱パネルを完成させます。
(2)つまり、圧力をかけるため密度が他のウレタン断熱メーカーよりはるかに高いのです。実際にウレタンの断面をみると、目が細かくなっているのが一目瞭然でわかります。
(3)そして、なぜ「FPの家」はウレタンを木枠に接着する方法をとっているのか?接着することで木とウレタンのそれぞれの剛性と強度が相乗効果をもたらし、圧縮強度がグーンとパワーアップするからです。地震のときは左右に揺れますが、こうした揺れにウレタン断熱パネルの圧縮強度が抜群の効果を発揮するのです。
(4)ウレタン断熱パネルを面構造にし、さらに剛性と堅牢さを維持させます。
ウレタンでもこんなに違う![工場生産型と現場生産型] ウレタン発砲は大変デリケートな素材なため、温度や湿度によって品質の出来不出来が左右され、その品質管理は非常に難しいのが特徴といえましょう。ウレタンは大別すると工場生産型と現場生産型があります。では、品質において工場生産型と現場生産型ではどのように違うのか、比較してみましょう。
<工場生産型>FP断熱パネル
●FP断熱パネルは、前者の工場生産型で、温度・湿度管理がしっかり行き届いており、四季の気候変化に合わせた原材料ブレンドをしています。また、朝・昼・夜毎に厳しく製品チェックをし、ムラのない一定な品質管理がなされています。工場で生産される注入式ウレタンパネルは、決められた体積に対する原材料をコンピュータで計算し、注入・圧力プレスして一定の大きさに成形します。したがって高密度なウレタンパネルが出来上がり、ウレタンのもっている性能が十分に発揮されます。
●また、FP断熱パネルは性能劣化がないため、何度でもリサイクルが可能です。
<現場生産型>現場発泡ウレタン
●現場発泡ウレタン(フリー発砲)は、後者の現場生産型で、ウレタン発砲の重要なポイントとなる温度・湿度管理に対応できません。また、原材料ブレンドの適切なコントロールができません。発砲量や厚さも一定ではなく、表面が凸凹しています。このようなムラの多い状態では測定もできませんし、性能・品質が曖昧となっています。
●さらに、現場発泡ウレタンは、工場生産の注入パネル1?当たり3分の2の量しか原材料を使用していませんので、ウレタンの性能が充分に発揮されません。
●また、将来、建物を解体する時、化学製品の分別回収になるため、相当なコストがかかることが予想されます。
A:お答します
ウレタンの発火温度は250℃前後ですから、木材とほぼ同じです。木材が燃えてしまうくらいの状態なら家全体に火がまわり、ほほ全焼状態になっているはずです。 さて、家の耐火対策には壁内に空気を入れないことが絶対条件となります。
ウレタンは空気を寄せつけない性質を持っています。FPの家は壁体内にそのウレタンを隙間なく密着しているので、空気が壁の中に入り込む余地がありません。火が壁の中に燃え広がろうとしてもそこでストップされ、表面が炭化するだけで留まります。例えば、電話帳を丸ごと火に入れても空気が封印されていますので燃えにくく、逆に電話帳を1ページずつ開いた状態にしていると、あっという間に燃えてしまいます。これとまったく同じ原理です。
そして、耐火対策において構造体も大事なポイント。FPの家は建物全体が機密性が高く密閉された状態になっていますから、外からの空気の流入を少なくし、家全体の延焼を遅らせることができます。また、各室に耐火性の高い石膏ボードを張り合わせていますので、出火室の中だけで消火します。つまり、「FPの家はベッドから出火したらベッドだけが燃え、室内で消火する家」とお考えください。
●壁のバリア(ウレタン断熱パネル)
●室内のバリア(石膏ボード)
●家全体のバリア(密閉された建物)
これがFPの家の耐火のための3大構造となります。 ところが、グラスウールでは壁体内に空気が入りやすいので火が壁体内を走ってしまいます。家が延焼してしまう理由の大半は壁体内を火が走り、上のほうに燃え上がることによるものです。耐火において、構造がいかに重要であるかがご理解いただけると思います。
ウレタンの発火温度は250℃前後ですから、木材とほぼ同じです。木材が燃えてしまうくらいの状態なら家全体に火がまわり、ほほ全焼状態になっているはずです。 さて、家の耐火対策には壁内に空気を入れないことが絶対条件となります。
ウレタンは空気を寄せつけない性質を持っています。FPの家は壁体内にそのウレタンを隙間なく密着しているので、空気が壁の中に入り込む余地がありません。火が壁の中に燃え広がろうとしてもそこでストップされ、表面が炭化するだけで留まります。例えば、電話帳を丸ごと火に入れても空気が封印されていますので燃えにくく、逆に電話帳を1ページずつ開いた状態にしていると、あっという間に燃えてしまいます。これとまったく同じ原理です。
そして、耐火対策において構造体も大事なポイント。FPの家は建物全体が機密性が高く密閉された状態になっていますから、外からの空気の流入を少なくし、家全体の延焼を遅らせることができます。また、各室に耐火性の高い石膏ボードを張り合わせていますので、出火室の中だけで消火します。つまり、「FPの家はベッドから出火したらベッドだけが燃え、室内で消火する家」とお考えください。
●壁のバリア(ウレタン断熱パネル)
●室内のバリア(石膏ボード)
●家全体のバリア(密閉された建物)
これがFPの家の耐火のための3大構造となります。 ところが、グラスウールでは壁体内に空気が入りやすいので火が壁体内を走ってしまいます。家が延焼してしまう理由の大半は壁体内を火が走り、上のほうに燃え上がることによるものです。耐火において、構造がいかに重要であるかがご理解いただけると思います。
A:お答します
では換気についてお話しましょう。当然のことですが、昔の家はすべて自然換気の家出した。自然換気は室内外の温度の差があるときや風力がある時に初めて換気としての能力を発揮するのですが、室内外の温度が一定だと空気が動かず、自然換気の機能はストップします。ということは室内の壁に生活のにおいが付着することになります。
さらには、一酸化炭素(CO)・二酸化炭素(CO2)・窒素酸化物(NOX)をはじめ、ダニの死骸や電気掃除機の使用による空気中に浮遊する粉塵、観葉植物の農薬、蚊取り線香の煙、タバコの煙等々。これでは室内汚染物質発生源に包まれた生活ということになります。そして住宅に使用されている有害物質の中でも、一番問題になっている建材の接着剤や合成樹脂に含まれるホルムアルデヒド。ぜんそくの発作などを引き起こすこうした有害物質が家中蔓延するとしたら家族の健康もSOSです。現代生活においてもはや自然換気でまかなうことは不可能なことです。
計画換気を分かりやすい言葉でいえば、「人口肺」をつけるようなものとお考えください。汚染物質等を強制的に排出し、新鮮な空気を入れる。汚染物質等が肺の中にずっと滞留していたら、健康によくないことはいうまでもないことです。家も同じことがいえます。家中つねに新鮮な空気にコントロールされていなければなりません。健康的に暮らすうえで、現代生活には計画換気は必要不可欠なものなのです。
では換気についてお話しましょう。当然のことですが、昔の家はすべて自然換気の家出した。自然換気は室内外の温度の差があるときや風力がある時に初めて換気としての能力を発揮するのですが、室内外の温度が一定だと空気が動かず、自然換気の機能はストップします。ということは室内の壁に生活のにおいが付着することになります。
さらには、一酸化炭素(CO)・二酸化炭素(CO2)・窒素酸化物(NOX)をはじめ、ダニの死骸や電気掃除機の使用による空気中に浮遊する粉塵、観葉植物の農薬、蚊取り線香の煙、タバコの煙等々。これでは室内汚染物質発生源に包まれた生活ということになります。そして住宅に使用されている有害物質の中でも、一番問題になっている建材の接着剤や合成樹脂に含まれるホルムアルデヒド。ぜんそくの発作などを引き起こすこうした有害物質が家中蔓延するとしたら家族の健康もSOSです。現代生活においてもはや自然換気でまかなうことは不可能なことです。
計画換気を分かりやすい言葉でいえば、「人口肺」をつけるようなものとお考えください。汚染物質等を強制的に排出し、新鮮な空気を入れる。汚染物質等が肺の中にずっと滞留していたら、健康によくないことはいうまでもないことです。家も同じことがいえます。家中つねに新鮮な空気にコントロールされていなければなりません。健康的に暮らすうえで、現代生活には計画換気は必要不可欠なものなのです。
A:お答します
人間は約36℃の体温をほぼ一定に保ち、身体の生理的機能を順調に行えるように身体の熱を調節しています。室内の環境要素として気温、湿度、気流速度および週壁面温度があります。これらを温熱四要素といいます。人間が家などの空間で、快適あるいは普通の状態で過ごすには、その室内の温熱四要素を【計画換気および冷暖房】を用いて調節する必要があります。
そして快適な住環境をつくるためにもっとも重要なのが湿度との関係です。例えば、摂氏80℃のサウナ室に長く入っていられるのは湿度がないからです。サウナ室に大量の水分(濡れたタオル等)を持ちこんだら、とても入ってはいられません。家も同様で適度な除湿対策が必要となります。同じ温度でも人間は湿度によって体感温度が変わります。アフリカの砂漠の木陰で気持ちよく昼寝をしていられるのも、気温が摂氏40℃あっても湿度がなくカラッとしているからなのです。
また、摂氏40℃で湿度が80%ある地域だったら、昼寝どころではありません。身体がすっかり消耗してしまうでしょう。日本のような夏蒸し暑い気象条件の国では、除湿対策は欠かせません。
【計画換気および冷暖房】は温度と湿度をバランスよく調整し、快適な住空間づくりに大切な役割を果たしています。
人間は約36℃の体温をほぼ一定に保ち、身体の生理的機能を順調に行えるように身体の熱を調節しています。室内の環境要素として気温、湿度、気流速度および週壁面温度があります。これらを温熱四要素といいます。人間が家などの空間で、快適あるいは普通の状態で過ごすには、その室内の温熱四要素を【計画換気および冷暖房】を用いて調節する必要があります。
そして快適な住環境をつくるためにもっとも重要なのが湿度との関係です。例えば、摂氏80℃のサウナ室に長く入っていられるのは湿度がないからです。サウナ室に大量の水分(濡れたタオル等)を持ちこんだら、とても入ってはいられません。家も同様で適度な除湿対策が必要となります。同じ温度でも人間は湿度によって体感温度が変わります。アフリカの砂漠の木陰で気持ちよく昼寝をしていられるのも、気温が摂氏40℃あっても湿度がなくカラッとしているからなのです。
また、摂氏40℃で湿度が80%ある地域だったら、昼寝どころではありません。身体がすっかり消耗してしまうでしょう。日本のような夏蒸し暑い気象条件の国では、除湿対策は欠かせません。
【計画換気および冷暖房】は温度と湿度をバランスよく調整し、快適な住空間づくりに大切な役割を果たしています。
A:お答します
まず、どんなに優れた家でも定期的なメンテナンスをしなくては、寿命には限りがあります。一番よい例として、ドイツの名車フォルクスワーゲンがあります。フォルクスワーゲンはもう20年前に製造中止になっているのに、今でも街を走っている光景を見かけることがあります。これは性能の良さもさることながら、製造中止になっていても、世界各地の整備工場でパーツごと交換部品が簡単に取り替えられるシステムが確立しているからです。だからこそ長持ちするし、いつまでも走っていることができるのです。
家についても同じことがいえます。ヨーロッパの家などは堅牢な特性に加え、はじめからメンテナンスのしやすい設計になっていることと、家は維持管理して長持ちさせるという意識がしっかりと根づいているからです。ちょっと窓や屋根が傷んできたからといって。家を改築しようとは考えません。
家を社会的ストックとして考えていますから、直したいところのメンテナンスだでけ済ませます。現にヨーロッパでは家のメンテナンスへの投資シェアが5割強も占めていることでもおわかりになると思います。 そしてもうひとつ。建てる前、建てた後の思わぬトラブルに備えての住宅の補償制度もしっかり確立して、お客様の信頼を得ることが大切です・100年住宅には「定期的なメンテナンスと補償制度」が重要なキーワードとなります。
まず、どんなに優れた家でも定期的なメンテナンスをしなくては、寿命には限りがあります。一番よい例として、ドイツの名車フォルクスワーゲンがあります。フォルクスワーゲンはもう20年前に製造中止になっているのに、今でも街を走っている光景を見かけることがあります。これは性能の良さもさることながら、製造中止になっていても、世界各地の整備工場でパーツごと交換部品が簡単に取り替えられるシステムが確立しているからです。だからこそ長持ちするし、いつまでも走っていることができるのです。
家についても同じことがいえます。ヨーロッパの家などは堅牢な特性に加え、はじめからメンテナンスのしやすい設計になっていることと、家は維持管理して長持ちさせるという意識がしっかりと根づいているからです。ちょっと窓や屋根が傷んできたからといって。家を改築しようとは考えません。
家を社会的ストックとして考えていますから、直したいところのメンテナンスだでけ済ませます。現にヨーロッパでは家のメンテナンスへの投資シェアが5割強も占めていることでもおわかりになると思います。 そしてもうひとつ。建てる前、建てた後の思わぬトラブルに備えての住宅の補償制度もしっかり確立して、お客様の信頼を得ることが大切です・100年住宅には「定期的なメンテナンスと補償制度」が重要なキーワードとなります。
A:お答します
他住宅メーカーの悪口を言うつもりはありませんが、まず構造体の性能が資産価値において一番重要であることを、お客様に伝えようとはしません。税法における法定耐用年数も、木骨モルタル住宅で20年、木造住宅で22年と低く、こうした税法での資産評価が家は30年持てばいいということに拍車をかけてしまいました。これが建物の資産価値をなくした根源です。
したがって売るための中心ポイントは見た目のよさの競演となっています。キッチン、浴室、洗面所など設備の豪華さばかりを着飾って見せ、お客様をごまかしている場合が多いのです。
しかし、どんなに豪華にした設備も5〜10年で資産価値がゼロになってしまいます。つまりは10年で資産価値がゼロになるものに対し、家の代償を払うことになるわけです。おまけに構造体や性能の不備から家が腐ってくるなど、後でその高いツケがどっと回ってきます。すぐにまた家を建て直さなければならないとしたら、人生の豊かさどころではありません。
また、100年もつ住宅を建てることは、個人資産形成の他、社会的ストックとしての意味合いからも、とても大切なことです。仮にFPの家の累積を4万棟で1兆円とした場合、これが30年もつか50年もつか100年で損失するかで、日本の社会的ストック損失にもつながります。欧米並みに家を100年以上もたせることは、個人の資産価値だけでなく社会的ストックの貢献にもなるわけです。
他住宅メーカーの悪口を言うつもりはありませんが、まず構造体の性能が資産価値において一番重要であることを、お客様に伝えようとはしません。税法における法定耐用年数も、木骨モルタル住宅で20年、木造住宅で22年と低く、こうした税法での資産評価が家は30年持てばいいということに拍車をかけてしまいました。これが建物の資産価値をなくした根源です。
したがって売るための中心ポイントは見た目のよさの競演となっています。キッチン、浴室、洗面所など設備の豪華さばかりを着飾って見せ、お客様をごまかしている場合が多いのです。
しかし、どんなに豪華にした設備も5〜10年で資産価値がゼロになってしまいます。つまりは10年で資産価値がゼロになるものに対し、家の代償を払うことになるわけです。おまけに構造体や性能の不備から家が腐ってくるなど、後でその高いツケがどっと回ってきます。すぐにまた家を建て直さなければならないとしたら、人生の豊かさどころではありません。
また、100年もつ住宅を建てることは、個人資産形成の他、社会的ストックとしての意味合いからも、とても大切なことです。仮にFPの家の累積を4万棟で1兆円とした場合、これが30年もつか50年もつか100年で損失するかで、日本の社会的ストック損失にもつながります。欧米並みに家を100年以上もたせることは、個人の資産価値だけでなく社会的ストックの貢献にもなるわけです。
A:お答します
社会問題にもなっている地球の温暖化問題。CO2等の大幅な削減が緊急課題とされていますが、その解決策としては家の消費エネルギーをゼロ・エネルギーに近づけること、100年住宅をつくりムダな産業廃棄物を出さないことが温暖化を防ぐ決め手になります。断熱・気密という寒さを防ぐという意味に考えるから、南の地域では断熱材は薄くてもかまわないという中断熱・中気密による住宅が登場してくるわけです。
北・南の地域に関係なく、消費エネルギーがゼロになることがよいわけで、環境負荷の低減になるわけです。家をゼロ・エネルギーに近づけるには、石油や電気などの消費エネルギーを極力使わない構造体と高い性能をもつこと。日本のように資源エネルギーが乏しく、そのほとんどを海外に依存している国では、資源エネルギーが永続的に価格保証されているわけではありません。仮にエネルギーがストップされて、冷暖房等の消費エネルギーが使えなくなったとしても、快適・健康に暮らせる住宅があれば、『ゼロ・エネルギーほど安い買い物』はないわけです。
また、家が100年以上もつとしたら、家2棟分の貴重な森林資源を伐採しないで済みますし、産業廃棄物の大幅な削減につながるわけです。それに構造体のウレタン断熱パネルは性能劣化がないため、何度でもリサイクルが可能です。 ゼロ・エネルギーと100年住宅。環境負荷の低減において、住宅メーカーの責任と義務がますます問われる時代になってきたのです。
社会問題にもなっている地球の温暖化問題。CO2等の大幅な削減が緊急課題とされていますが、その解決策としては家の消費エネルギーをゼロ・エネルギーに近づけること、100年住宅をつくりムダな産業廃棄物を出さないことが温暖化を防ぐ決め手になります。断熱・気密という寒さを防ぐという意味に考えるから、南の地域では断熱材は薄くてもかまわないという中断熱・中気密による住宅が登場してくるわけです。
北・南の地域に関係なく、消費エネルギーがゼロになることがよいわけで、環境負荷の低減になるわけです。家をゼロ・エネルギーに近づけるには、石油や電気などの消費エネルギーを極力使わない構造体と高い性能をもつこと。日本のように資源エネルギーが乏しく、そのほとんどを海外に依存している国では、資源エネルギーが永続的に価格保証されているわけではありません。仮にエネルギーがストップされて、冷暖房等の消費エネルギーが使えなくなったとしても、快適・健康に暮らせる住宅があれば、『ゼロ・エネルギーほど安い買い物』はないわけです。
また、家が100年以上もつとしたら、家2棟分の貴重な森林資源を伐採しないで済みますし、産業廃棄物の大幅な削減につながるわけです。それに構造体のウレタン断熱パネルは性能劣化がないため、何度でもリサイクルが可能です。 ゼロ・エネルギーと100年住宅。環境負荷の低減において、住宅メーカーの責任と義務がますます問われる時代になってきたのです。